
易経「繋辞下伝」を読み解く31
易の興(おこ)るや、それ中古においてするか。易を作る者は、それ憂患あるか。(繋辞下伝第7章第1節)
「易の興(おこ)るや、それ中古においてするか。易を作る者は、それ憂患あるか。」
「易が盛んになったのは、中古においてであろう。易を作った人は、そもそも憂い悩みがあったのであろう。」
第7章、易の起源に迫ります。
孔子は易経の研究が盛んになったのは、伏羲が易経を成立させた太古(上古)ではなく中古、禹王の興した夏王朝、湯王が興した殷王朝であろうと想起します。文明の発展と共に、大きな集落が都市へと発展、人口も増加する中で、農作物の収量の多寡、天災の有無、果ては外敵の襲来などが為政者の関心事項となります。
これは易経の卦象の連続性を説き表す「序卦伝」を読み解くと、その関連性や発展性が窺えます。
“天地ありて然る後に万物生ず。天地の間に盈(み)つる者はただ万物なり。故にこれを受くるに屯(ちゅん)をもってす。” 乾坤あってそうしたあとで万物が産み出された。乾坤の間に満ちるものはただ万物だけである。ゆえに乾坤の卦の後に水雷屯の卦が置かれたのである。 “屯とは盈つるなり。屯とは物の始めて生ずるなり。物生ずれば必ず蒙なり。故にこれを受くるに蒙(もう)をもってす。” 屯とは陰陽が満ちる事である。屯とは物が始めて産み出されることである。産み出されたばかりの物、かならず蒙である。ゆえに水雷屯の後に山水蒙の卦が置かれたのである。 “蒙とは蒙(おろ)かなり。物のおさなきなり。物おさなければ養わざるべからず。故にこれを受けるに需(じゅ)をもってす。” 蒙とはおろかである。幼い状態である。幼ければ養い育てなければならないのである。ゆえに山水蒙の卦の後に水天需の卦が置かれてのである。 “需とは飲食の道なり。飲食すれば必ず訟(うった)えあり。故にこれを受くるに訟(しょう)をもってす。” 需とは飲食の道である。飲食すればかならず争い事が起こる。ゆえに水天需の卦の後に天水訟の卦が置かれたのである。 “訟えには必ず衆の起(おこ)るある。故にこれを受くるに師(し)をもってす。” 訴訟事には必ず大衆が集まり徒党を成すことがある。ゆえに天水訟の卦の後に地水師の卦が置かれたのである。 ”師とは衆なり。衆なれば必ず比(した)しむところあり。故にこれを受くるに比(ひ)をもってす。” 師とは集団である。集団に属せば人は争うことをやめ必ず親しみ和す。ゆえに地水師の卦の後にこ水地比の卦が置かれたのである。(序卦伝 第1節から第6節)
統計学ととしての易経
おそらく伏羲が作ったであろう64卦は初めは卦象だけで特に警句や戒めを必要としなかったはずです。
しかし、人間の営みが発展拡大するにつれて、様々な障害や衝突が起き、繰り返される災害に不便や危機を感じるようになっていきます。そういった時に、発生した事象、事件や事故を易経に照らし合わせ、膨大な事実の積み重ねを中国古代の為政者や賢者は繰り返していったのでしょう。
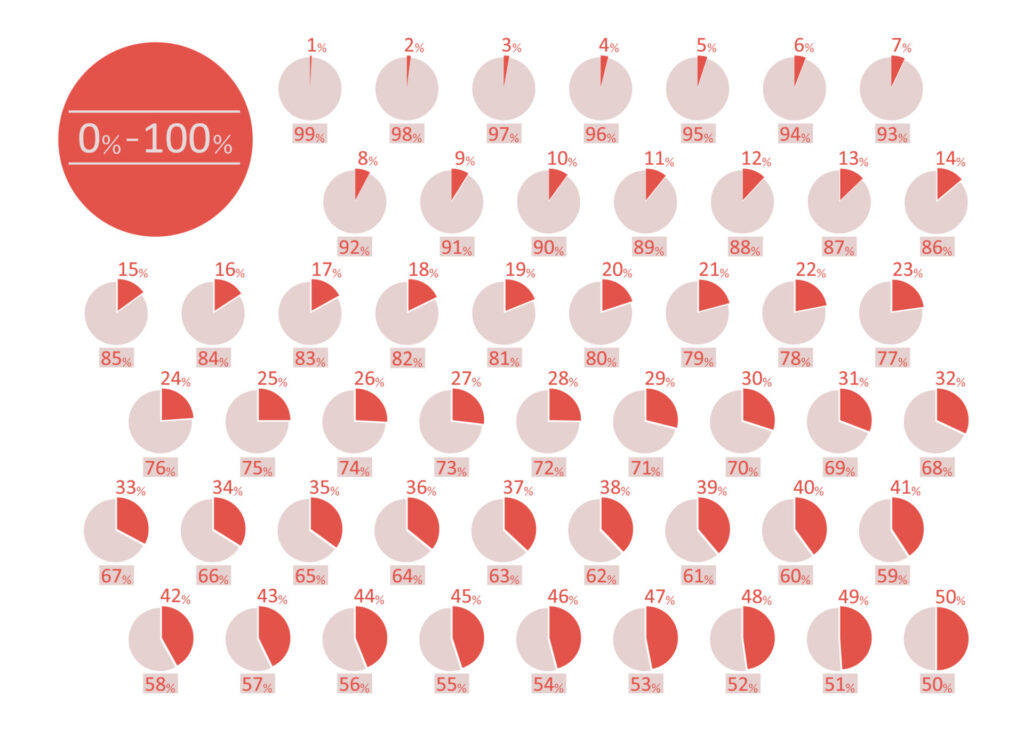
農耕技術の発展と共に、人間の生活は流浪から定住へと変化、それと同時に所有の概念が生じ、都市の形成と共に集団への帰属意識が芽生えていきます。
その過程で、生活を営む上で様々な障害や天災、事故や事件の予兆を事前に察知し、その危機を未然に防いだり、避けたい…という願いが生じます。
そのような中で、易経の研究が進む…おそらくそれはつぶさに日月星辰の運行の観察、則ち天文学より発展していったと思われます。それが時の概念の発見と暦の発明へとつながり、暦や時と天文学が融合した時に初めて統計学としての易経に焦点が当てられます。
哲学としての易経とその融合
しかし統計学としての易経にとどまっていたのであれば、ある程度のデータの集積を見たところで、一定の結論を得てそれ以上の発展は見なかったでしょう。
そもそも万事幸福、吉の状態が続いていたのであれば、危機を脱したい、未然に防ぎたいという需要は生まれません。危機の無い環境はそこに住まう者の生活や文化を弛緩させ、その発展発達の歩みをとどめてしまいます。

しかし、生活するうえで様々な生と死に直面しその意義を考える時、目に見えない存在、形而上の視点に立って物事を捉える様な,いわば哲学的に易経を捉えた時、それまでの易経に見出していた価値とは全く異なる価値観を生じるに至ります。
それまでの形而下的な見方と対峙する新たな易経の捉え方です。さながら陰と陽の交わる作用から卦象や万物が生じるかのように、形而上と形而下の融合により易経はそれまでの統計学としての捉え方にとどまることのない普遍性を帯び、物質論的にも精神論的にも色あせることなく、時の流れにも風化することの無い経典としての発展を見ます。
その営みを孔子は「偉業」として称えるのです。




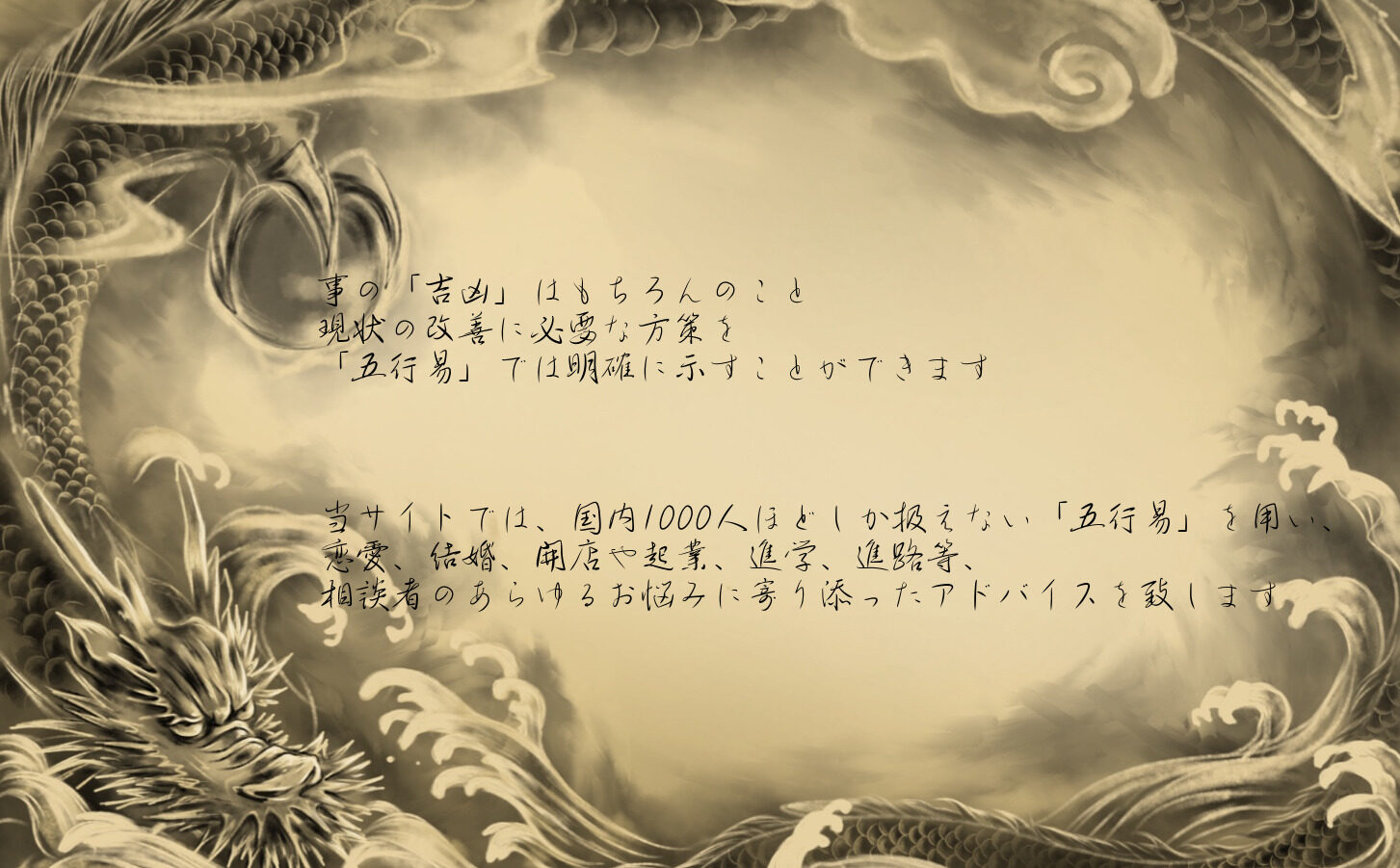
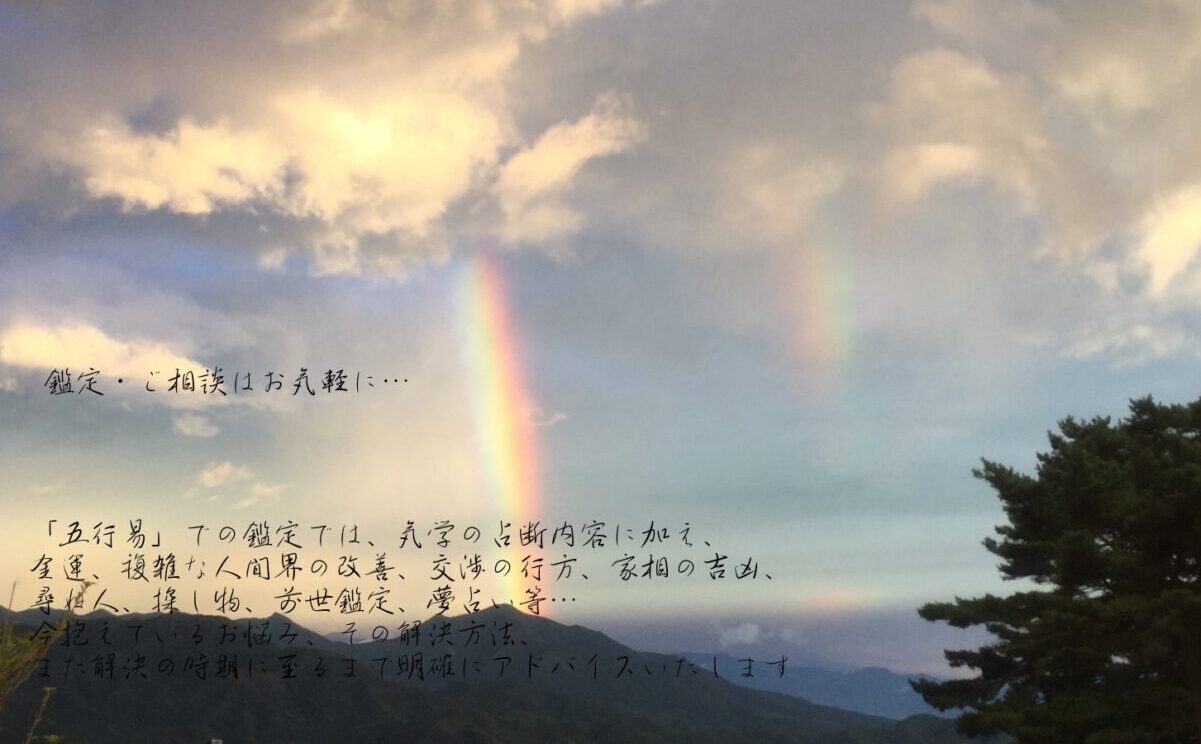


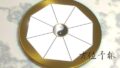
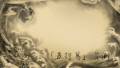

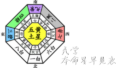



コメント