
易経「繋辞下伝」を読み解く49
「将に叛かんとする者は其の辞慙(は)じ、中心疑う者は其の辞枝(わか)る。吉人の辞は寡(すくな)く、躁人(そうじん)の辞は多し。善を誣(し)うる人は辞游(うか)び、其の守りを失う者は其の辞屈(かが)む」(繋辞下伝第12章第7節)
「将に叛かんとする者は其の辞慙じ、中心疑う者は其の辞枝る。吉人の辞は寡く、躁人の辞は多し。善を誣うる人は辞游び、其の守りを失う者は其の辞屈む」
「今まさに道義に反するようなことを行おうとする者の言葉には、心のやましさを感じさせ“恥じ”を感じさせる。

心の中に迷いがあって悩みがある者の言葉は、一環としておらず、二転三転する。
徳のある立派な人物の言葉は少ない言葉でその真理を言い当てる。
徳が少なく底の浅い人物は、言いつくろうことに終始するので、口数が多くなる。
善人を誹謗して貶めようとする者は、出まかせばかりでその言葉に重みが無い。

守るべき信念や志を失っている人は、その言葉にも節操がなく信頼が置けないのである。(したがって、易の爻辞もこのようにその卦象の爻位が、人間関係における情緒を表す物であるから、占って得た爻の爻辞をよくよく味わって解釈すべきである)」
易経に見る老子と孔子の思想の共通性
孔子が繋辞上伝・下伝で指し示す“聖人”と、老子がその著書の中で示す“聖人”のその対象は同じです。易経を生み出した伏羲、更にその節理を以て万民を教導した尭・舜・禹等の賢王です。
孔子も老子もその思想の中で人間が究極的に目指す存在として「聖人」をあげるが、そのアプローチは正反対であることは過去の読み時で指摘したところです。


ところで、繋辞下伝の最終章であるこの一節、孔子の述べることと同じようなことを老子は指摘しています。
「真言は美ならず。美言は真ならず。善なる者は弁ぜず、弁ずる者は善ならず。智者は知らず。知る者は智者ならず。聖人は積まず。ことごとく人の為にし、己はいよいよ有す。ことごとく人に与え、己いよいよ多し。天の道は、利して害さず。聖人の道は為して争わず」(老子道徳経81章)
「真理を表す言葉は決して耳触りの良い言葉ではない。耳触りの良い言葉は真理ではない。善人は口数は少ないし、口数が多い物に善人は居ない。本当の智者は知識をひけらかすようなことはしないし、その知識をひけらかすような人物は本当の智者とは言えない。
聖人は己のために積み増すようなことはしない。ことごとく人のために尽くしていながら、結果としてますますその人徳が積み増されていくのである。ことごとく人に与えながら、結果自身が多く持っていることとなる。天道とは何かを利することに終始して、何かを害するようなことはしない。聖人の歩む道も何かを成すうえで誰かや何かと争うようなことはしないのである」
老子の述べるこの81章もまた、老子の著書「道徳経」の最終章です。

老子も、孔子も易経に対するその理解は、陰陽の作用、則ち宇宙の法則は、陰の作用も用の作用もその方向性は「生成化育」にあり、またその作用を決して誇示したり、誰かに強要するようなことはしない…であり、その易経の摂理に通達しその摂理を以て万民、万物を利する聖人の域に至るまで、自身を高めるべきだ…と究極の目標に聖人を充てます。
孔子はその聖人に至るまでの過程を「君子・大人」とその過程を明確にし、その域に達するための手段や方法を厳格に定めます。これが儒教、論語の厳しさであり優しさでもあります。
一方で老子は究極目標としての聖人は掲げつつ、その過程を強要したり、その手段や方法には寛大ですが、これが老子の優しさである一方で厳しさでもあります。
易経という捉えどころのない真理を目の当たりにした時に、孔子の述べる所は厳格です。
一方で明確にその方向性を示すので易の示す道筋の手がかりがつかみやすいが、その遠大な行程に時として凡人はため息をついてしまいます。
老子の述べる所はその方法も自由であるし、厳格に拘束するものではないので、老子の道を歩む者には容易く着手できます。
一方でその道程や方法は明瞭に示されないために、時として凡人は不安に駆られてしまいます。
易経の教えは、結果として何かに固執したり、何かに捕らわれることを嫌います。従って孔子の説く方法が正解でもないし、老子の説く方法もまた正解ではありません。
大切なことは“問う力”
房主は周易と五行易の垣根は存在しないと考えます。
大切なのはその時、その瞬間に「答え」を得たい…と願う刹那の強い思い、“念”ですから、その思いさえしっかりと明確であれば、得られる卦象を以て周易的な解釈、五行易的な解釈どちらをもってしても共通の答えを得ることはできるのです。
易占に携わる者として常々感じることは、
易経は本であって読むものに非ず
思想、哲学であって学ぶものでは無い。
本を読むにしても、易経に学ぶ…にしても、何かそこにしがみつくような執着や、依存性を感じさせます。
本当に易経の摂理を体得したいのであれば、書として読む、学ぶという具体的な行動よりも先に「感じる」という感性が大切です。
真理を得たいと易経に真正面から向かい合い、追及すると磁石の同じ極同士が離れあうように、追い求めても、その真理はするすると離れていってしまいます。
それよりもむしろ、易経は常にそこにある、誰もが息を吸ったり、水を飲むような行為と同様に、ごく当たり前の存在として身近に“感じる”程の距離感で相対する時、フッとその真理、その答えが目の前に示されるのだと思います。
「入力不力」(あいだみつを)
何かに悩んだ時、躓いた時に「どうすべきか?」という“問い”を強く心に念じ、その後はその答えが自然ともたらされるのを悠然と待つように易経に相対した時に、必ずその答えは示されます。
それは必ずしも言葉とは限らず、肌で感じる風の存在、風が運ぶ花や草木の香り、あるいは鳥のさえずりや遠くで轟く雷鳴かもしれません。
その感覚、その感性を鋭くするところに易経の理解を深化させるヒントが隠されていると感じているところです。




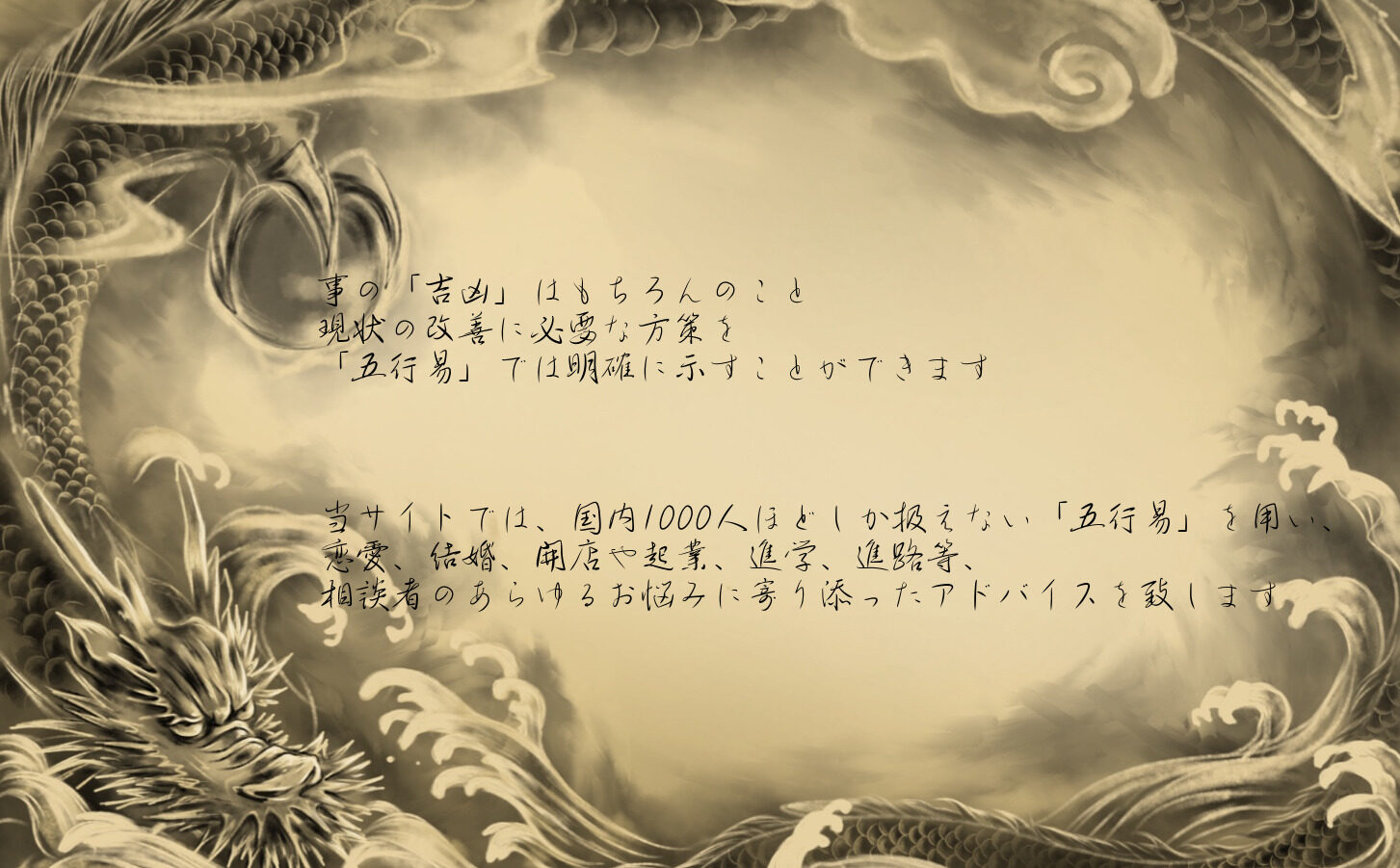
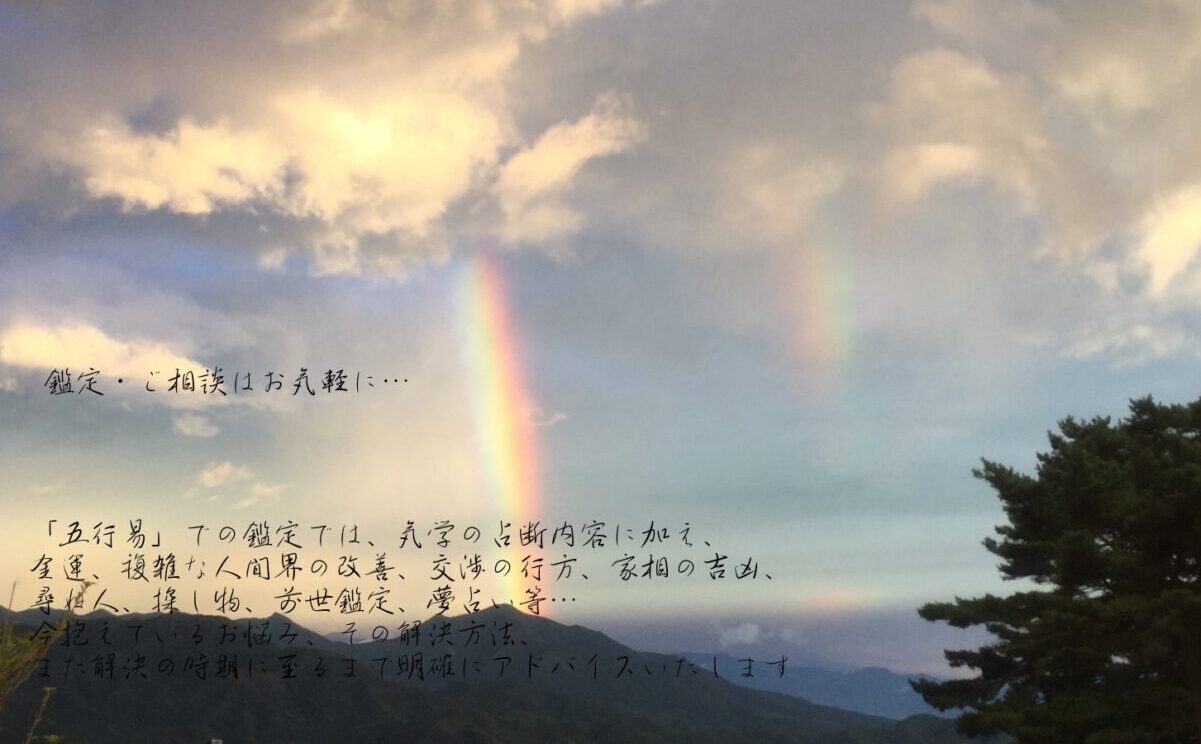



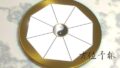
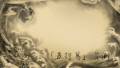

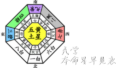



コメント