桜田虎門「五行易指南」現代語訳 114

○太歳爻
太歳爻が子孫や妻財を帯びる時は吉。その他父母、兄弟、官鬼が帯びる時は良くない。
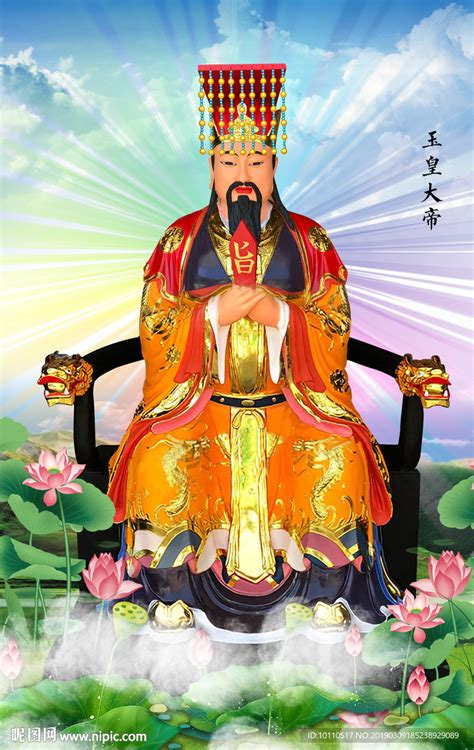
太歳爻が兄弟を帯び発動する時は、その年は風が多い。特に兄弟を帯びる太歳爻が世爻を剋するような時は、風害を患える。
太歳爻が官鬼を御帯びて発動する時は雷が多い、あるいは荒天の多い年である。ただし占って卦中に官鬼が現れない卦を得た時、あるいは年月日の暦も官鬼を帯びない時、あるいは卦中に現れた官鬼が衰弱である場合はその年は災害の少ない穏やかな歳である
太歳爻が父母を帯び発動する時、子孫が衰弱中を得たのであれば、その年は水害が多い年である。
太歳爻が妻財を帯び発動する時、卦中父母爻が衰弱する時は日照りや干ばつを憂う
○官鬼爻
官鬼が火行の地支を帯び発動するときは火災が多い年である。発動する官鬼が世爻を剋したり、冲したり、生じたり、合することが無い時、あるいは応爻を剋したり、冲したり、生じたり、合するは、自身はその火災に巻き込まれることは無く隣人の災害とする。
もし発動する火行の官鬼が無い卦の発動ならば自家に近く、外卦の場合は遠い。(※)(※易照注・この概念は重要で、世爻応爻の位置に関わらず内卦は世爻サイド、外卦の場合は応爻サイドという考え方は近代五行易でも通用する。特にこの概念は反吟や伏吟、三合会局においても同様に判断できる)
官鬼爻が水行の地支を帯びて発動する場合は水害を憂う。この場合も外卦の官鬼の発動ならば遠方での水害、内卦の発動ならば近郊での水害の発生を憂うが、いずれの場合も世爻を剋、冲、生合しなければ自家に被害には及ばない
官鬼爻が金行の地支を帯び発動する時は、軍事的な混乱がある。応爻を剋したり、冲する。或いはこの時五爻を生合するような場合は、政府の命令で自身も兵役に就くような事態に遭遇する。

ただし外卦の官鬼の発動であったり、化出官鬼の場合で、これが五爻を剋したり、冲するとき、あるいは太歳爻を剋すような時は、外敵、他国より軍事侵攻がある。
あるいは官鬼が内卦外卦に両現し、共に発動する時はその騒擾は一か所にとどまらず、各地に飛び火すると判断する。ただしいずれの場合も、官鬼が回頭の剋となったり、月日暦から剋冲を受けたり子孫爻の剋を受けるような場合は、大きな騒乱とはならない。
一方で休囚の官鬼の発動ならば、百姓の一揆や一般国民の抗議活動と取る
官鬼が上爻に現れ発動する、あるいはこの時白虎を伴う場合は疫病の流行である。もしこの官鬼が世爻を剋する場合は、その疫病で多くの死者がでる。ただし子孫爻の発動がある場合は、流行するも死者は多くない。

発動する官鬼に朱雀が付帯して世爻を刑したり、剋する場合はイナゴなどの虫害がある。
発動する官鬼に勾陳が付帯する場合は凶作を憂う。もし世爻が官鬼を帯びたり、発動する官鬼が世爻を剋する場合は凶作である。妻財が兄弟に化す回頭の剋であったり、妻財の発動とともに官鬼が発動する場合は飢饉を憂うる
発動する官鬼に玄武が付帯し、世爻を剋する時は盗賊、犯罪の多い年である。もし官鬼が金行の地支を帯び、太歳爻であったり五爻を冲、剋する時は謀反、政変を企てるものがある
凡そ上爻が官鬼を帯びて発動する時は、何かと異変、天災が多い年である
発動する官鬼に螣蛇が付帯して、本卦本宮が乾宮(金)である場合は天候に変異多い年である。
本卦本宮が震宮(木)であるときは、雷の変異がある。積乱雲が発達して雷鳴がとどろくのような様子。
本卦本宮が艮宮(土)であれば山に変異が多い年である。地滑りやがけ崩れの類
本卦本宮が坤宮(土)ならば地震がある。もし刑が成立する象であれば地割れなどの被害多い本卦本宮が坎宮(水)で、官鬼が父母に化すならば大雨である。洪水などの水害の類。

本卦本宮が巽宮(木)で、官鬼が兄弟に化すならば風害を憂う。強風や熱風、寒風等。兄弟を化出しない場合は、家畜の伝染病、農作物の病氣である。
本卦本宮が離宮(火)であれば、日食等の天象の変が起きる。皆既日食、部分日食、金環食、あるいは日輪が生じる等。もし、官鬼が午(火)を帯びるならば必ず大異変がある。流星、小惑星の落下等。(※)(※易照注・原文“天火”より推測)
本卦本宮が兌宮(金)ならば井戸や沼や池の変異である。
ただしこれらの官鬼が空亡の発動であったり、発動先が空亡に化す、あるいは官鬼爻が冲散する場合は、杞憂に終わる。またこの時異変がある方位を知りたい場合は、官鬼の帯びる地支に該当する方位方向から推断せよ。
またこの時も内卦の官鬼ならば近郊、外卦ならば遠方と断じるのは前述の通りである。
○子孫爻
子孫爻が旺相で妻財が空亡せず、官鬼が衰弱且つ安静ならばその年豊作である。また子孫爻が世爻を生じ、あるいは六合卦を得たのであれば、気象は安定し農作物には程よい雨や風が調うだろう
旺相の子孫を得て、官鬼や兄弟が空亡する、あるいは官鬼や兄弟が伏神するときは国家安泰、泰平の歳とする。
夏や冬の寒暑を推断する時は、地支の水行、火行の爻を見て判断する。この時、天候占のように父母が旺相ならば寒い、妻財が旺相ならば暑いと判断してはならない。
火行の爻が旺相発動して世爻を剋する場合は酷暑。水行ならば極寒。一方で例えば水行の爻が空亡したり、墓絶(※)する場合は暖冬である。火行ならば冷夏である。
(※易照注・原文は死絶。12運は病・死・墓・絶の順なので墓絶とした)

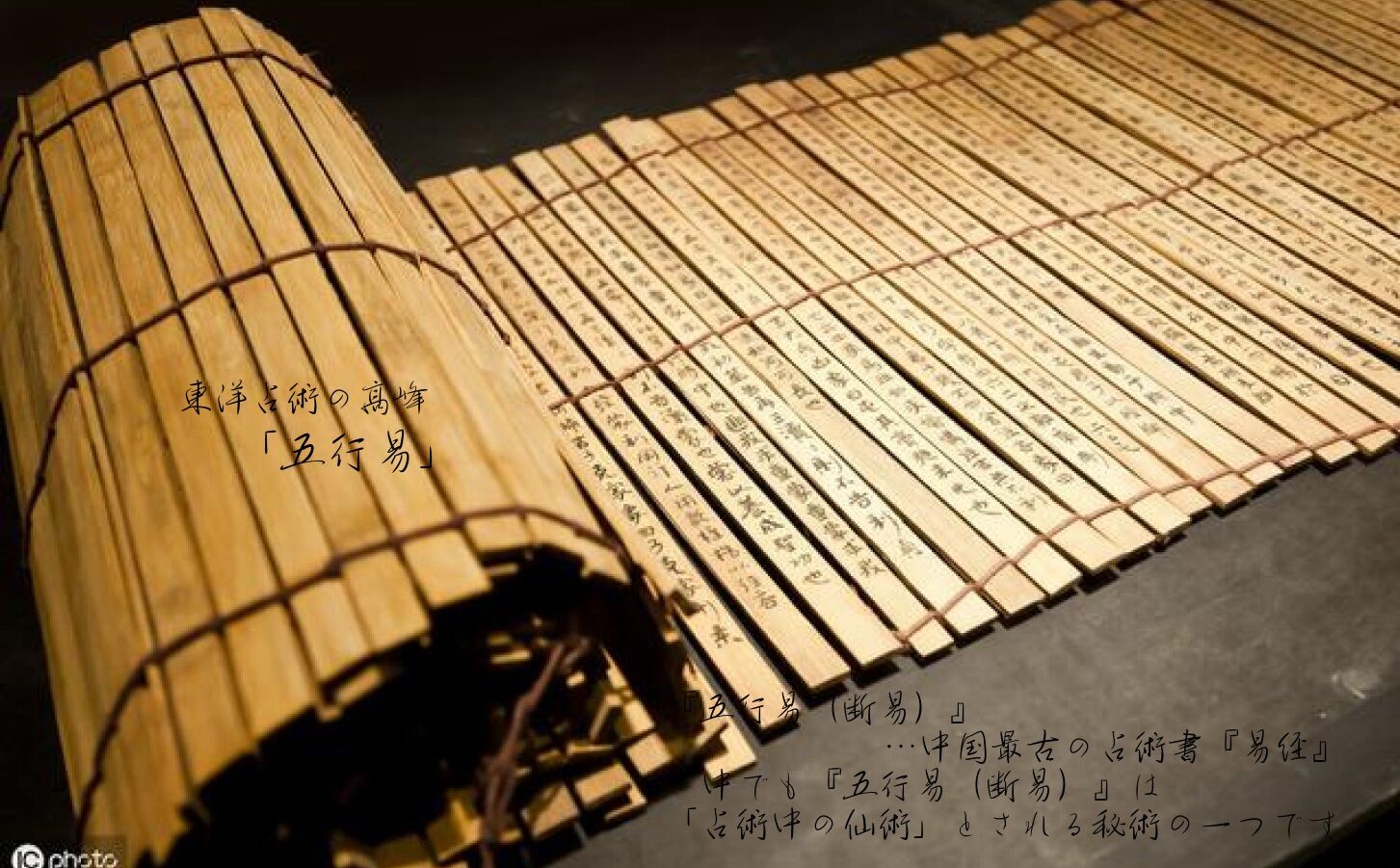
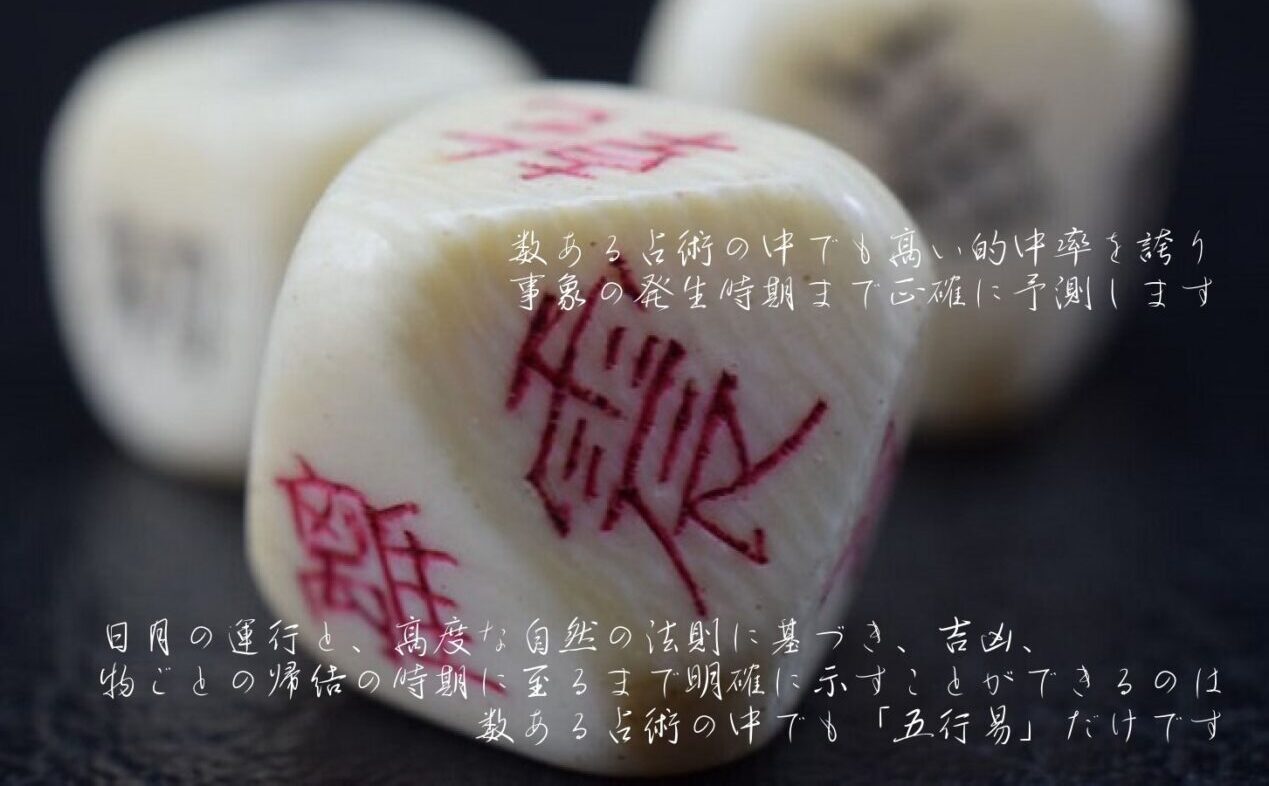
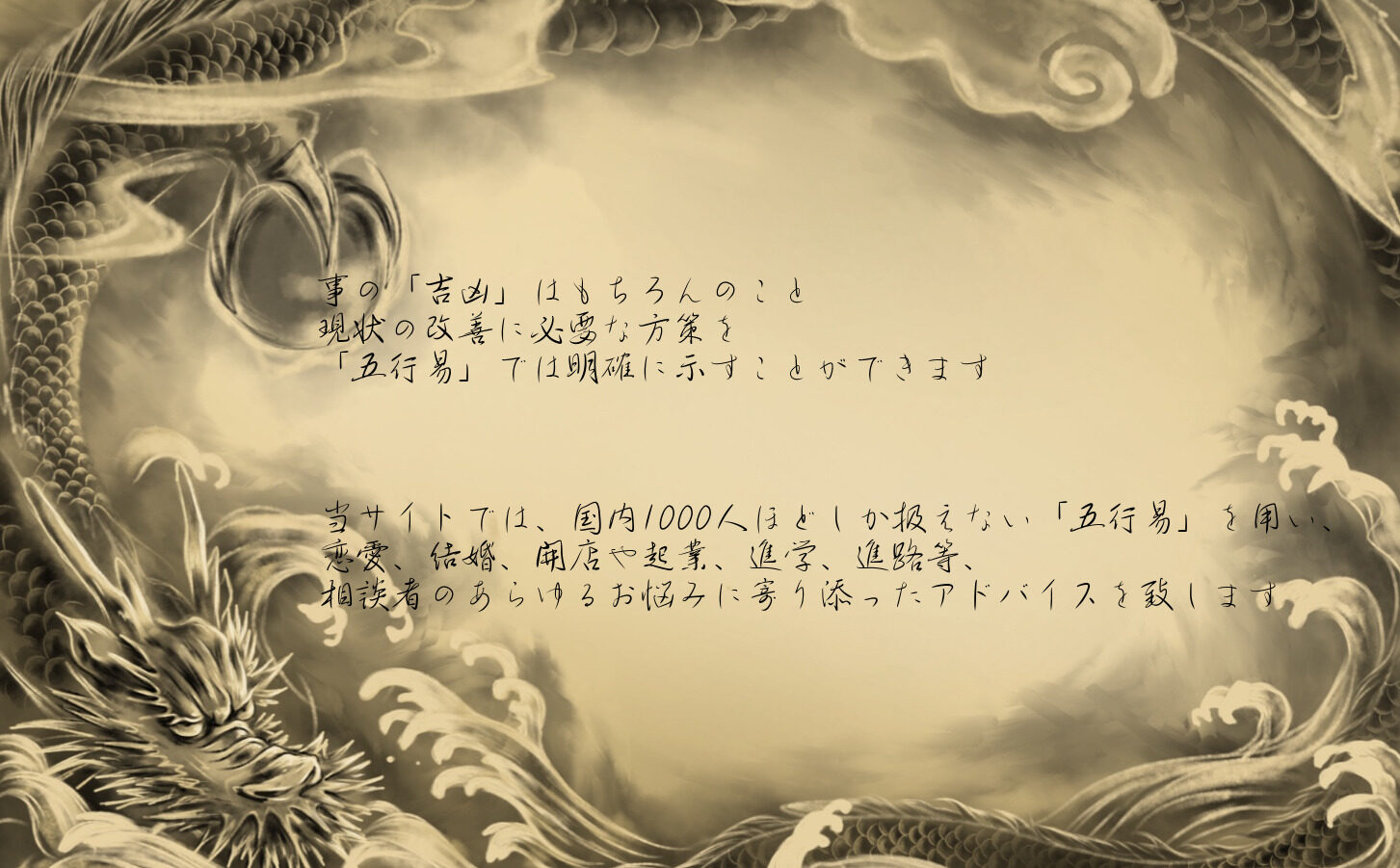
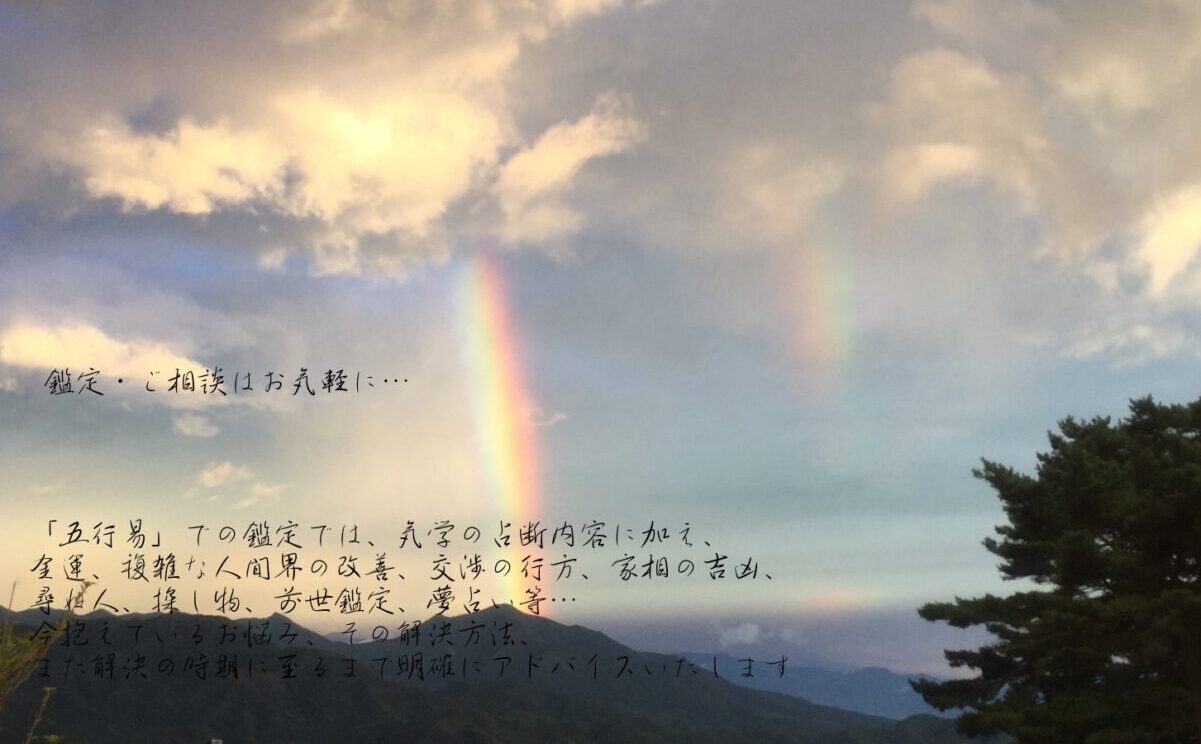
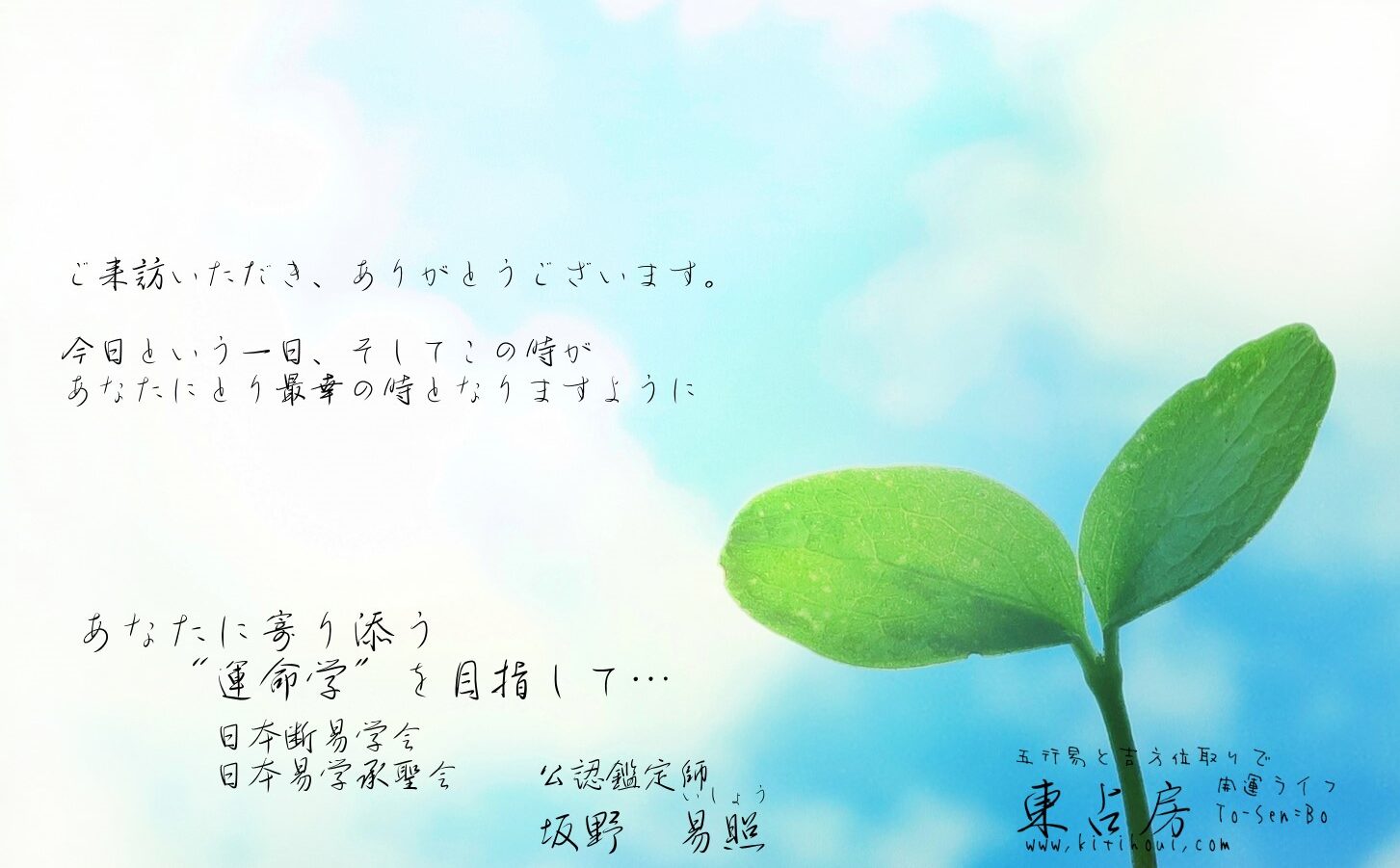
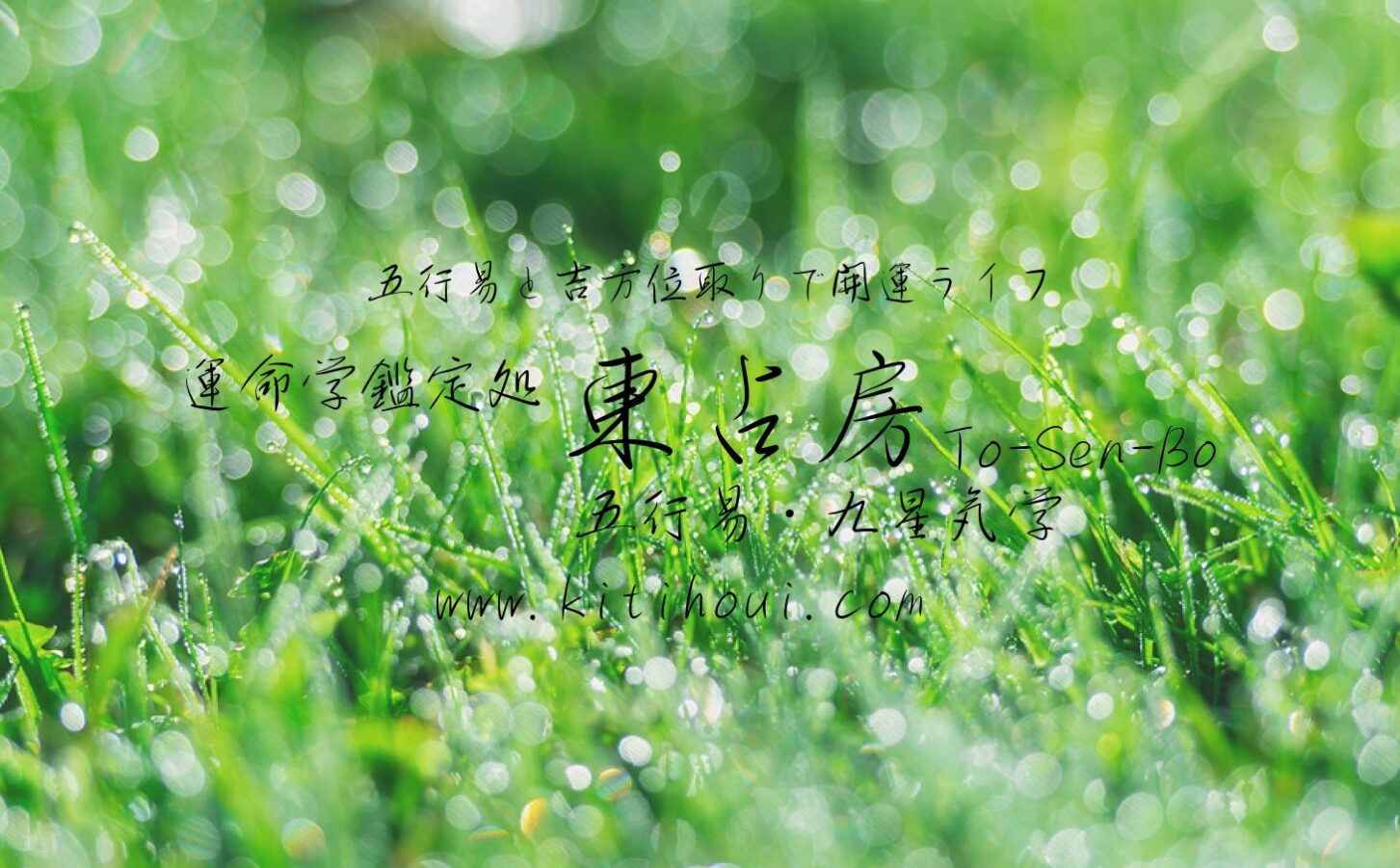
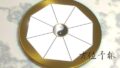


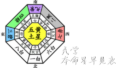



コメント